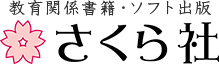【横山験也のちょっと一休み】№.3724
昨年の暮れに、さくら社から初めて絵本を出しました。
『おじばさん』です!!
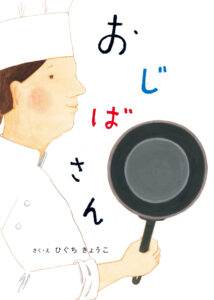
『おじばさん』が本になり手に取って読んでみると、心がホッとしました。
そんな気分になれることが嬉しくて、時折読み返しています。何回読んでも心温まります。
これを機に、ずっと以前からいつかは読んでみたいと思っていた児童文学を読んでみることにしました。近くの公民館図書室で借りてきて読んでいます。当然、線は引けません。折れ目も付けられません。
ちょっと、グッと来たところは、手元のメモ用紙にメモをするようにしています。といっても、1冊に1つか2つです。
児童文学を読んでいた時に、これもまた以前から思っていた国語の物語文の授業について、頭が少しめぐりました。物語文の授業の奇妙さです。
奇妙だなぁと思っていたのは、先生の問いと、問いに対する子ども達の答えです。
例えば、ある場面での登場人物の気持ちを問うことがあります。問われたので、子ども達も答えます。「嬉しかったのだと思います」などと。
このような答えは、豊かな場面の表現から、登場人物の心のありようを簡潔に言い表す表現です。物語文の持つ豊かさからは遠のきます。
また、簡潔なので、時として、先生は「どうしてそう思ったの」と聞くことがあります。それについても、「~~だから」などと場面と自分の言葉とのつながりの説明をします。
私が奇妙だなぁと感じていたことは、子どもの答えが説明になっていることです。物語文はその表現の素晴らしさから感動をするのですが、授業では、なぜか説明を求める形で答える問いが多いのです。理屈を答えるといってもいいかもしれません。
Why(なぜ)を問うといいという考え方もあります。が、なぜと問われたら、説明をすることになります。説明文の授業ではない物語の文で説明を求められます。そういうときもあって良いのですが、基本的に筋が違うような気がしています。
心情曲線を描く授業もあります。数理的な世界に子ども達をいざないたいのかもしれません。物語の世界からは遠のいているようにも感じます。
気持ちがどう変化したかを考える授業もあります。変化を明確にするには説明するしかありません。物語から論理の世界へ頭を連れていかれる感じがします。
こんなことがずっと以前から国語の授業の持つ奇妙さとして感じていたのですが、では、どうしたらよいのかと言うことになると、とんと浮かんでくるものがありません。
何も浮かんでこないので、私の感じている奇妙さは、単なるひねくれたものの見方なのかもしれないとも思っていました。
ですので、奇妙と思いつつも、自らの感覚は引っ込めているしかありませんでした。
そこに児童文学が面白いヒントを与えてくれました。
『赤毛のアン』です。
アンの想像力はすばらしいです。惹かれるものがあります。
物語文も想像力で描かれています。
何か通じるものを感じ、この想像力を国語の授業で培うことができたら、それは物語の文の授業としてとてもいいのではないかと思えています。
どうしたらよいかの一つのポイントとなりそうなのが、今、思いついている「赤毛のアン読み」です。でも、まだまだです。時間をかけて少しずつ組み立ててみたいと思います。
—
下の本は道徳の授業の本です。