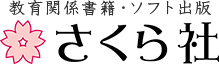【横山験也のちょっと一休み】№.3750
日曜日に「ジョナサンの会」が開催されました。
今回は、珍しく8人の参加で、過去最多となりました。
城ケ崎先生が鹿児島から戻ってきたので、再び司会を担ってもらいました。時間配分を気にしながら、きっちり5時に終了させてくれました。たいしたものです。
提案されたレポートは7本。
昔のようなコテコテの実践レポートは無くなり、経験や学術の積み重ねによる感心度の高い所の内容が多くなっています。傾向としては考えさせられる内容が多くなっています。
そんな中、ICT関連で最先端の情報を提供し続けている佐々木先生のレポートは目を見張りました。今回は、ノーコードで作れるアプリのサイトが紹介されていました。しかも、数十秒で1本が仕上がります。何時間もかけて、時には数日かけて、やっと1本という私から見ると、驚愕的な世界です。自分でもアプリを作ってみたいけど、コードは勘弁してほしいという人には、たまらないでしょうね。
面白い時代になりました。
また、城ケ崎先生のいじめの温床の発見、それへの対処のレポートは、会が終わった後も、あれこれと考えました。考えたくなったのは、城ケ崎先生がレポート提案の直後に「これをシステム1、システム2で考えるとどうなるか、教えてください」と言ったからです。この問いに対して、私も含め、良い感じの返事がありませんでした。
そうして、つらつらと思っていると、システム1システム2でストレートに考えても、考えにくいことが分かってきました。
システム1、システム2は脳の現象なので、進化教育学ではもう少し枠組みを大きくして把握した方が見えやすくなります。
そう言うことに気づくヒントになったのは、川合先生の退職後の心理の変化のレポートです。アメリカの老齢学の研究者アチュレイの「七つの段階」です。この七つの段階は、進化教育学で重要な要素と私が考えている「はじめの指導言」と似ています。似ているのは、物差しを示していることです。また、方向性があることも似ています。似ていないのは両極が不明瞭であることと、目的意識の無い事です。
城ケ崎先生のいじめの温床のレポートは、意図的にいじめの発生しない方向に向かわせようという意識が教師の側にあります。「はじめの指導言」ではこの目的意識の存在が実に重要と、川合先生のレポートから理解が進みました。
お陰様で、「はじめの指導言」の構成要素が<物差し><両極><方向性><目的意識>と4つ必要と分かりました。
これを使って、城ケ崎先生のいじめの温床と対策のレポートを見ると、いろいろと見えてきます。子ども達のシステム1を起動させるには何をどう伝えるべきか。また、子ども達にシステム2を使って考えさせるために何を検討させるのか。それを1つの出来事せずに、目指す方向へ歩ませていくにはどこに力を入れるべきか。これらの事が、きれいに見えてきます。
私のレポートは「論理的説明」と「直感的説明」です。これは算数教育を進化教育学からとらえ直し、新しい授業のあり方を考えていく、そのしょっぱなの部分です。しばらくは、ここを掘ろうと思っていましたが、入ってくる情報には算数が少なく、学級づくりが多いので、両方をゆっくりと研究していきたいと、そんなことをふと思いました。
ジョナサンの会は面白いですね!!
—
進化教育学から見ると、この本に書いてあるいろいろなアイディアは、実に理にかなっていると感じています。どれもいい本です。
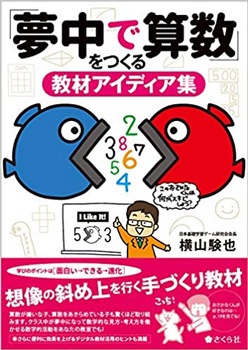 |
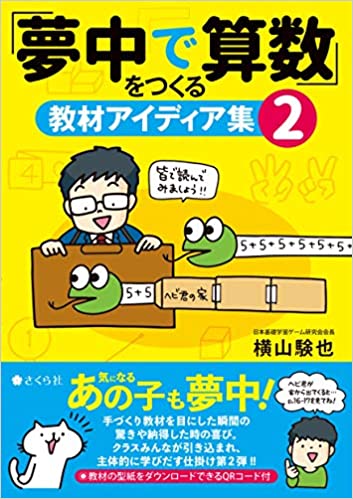 |
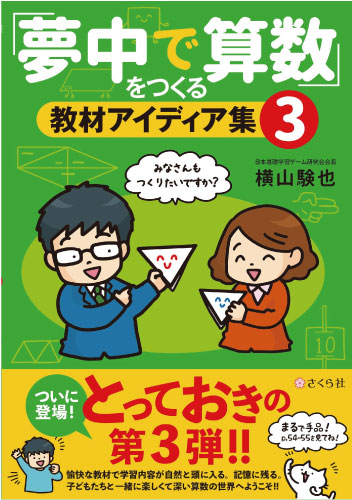 |