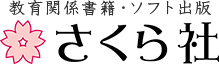【横山験也のちょっと一休み】№.3737
ジョナサンの会に参加しました。
参加者5名。5人のレポートを検討していたら、あっという間に3時間半ほど経ちました。それだけ、一つ一つのレポートが面白く、ワイワイと話し込んでいたのです。

今回は、珍しく細かいところを質問しました。
・大人とのコミュニケーションを通して感情がはぐくまれる
これは集団社会化説からすると主たる内容にはならいので、そこらあたりを諸野脇氏に聞いてみました。回答を得たらレポーターも他者も話し始め、結局はシステム1としてあがってくる感情は、まずはそのまま受け止め、それを行為に結び付ける時にどう行うかの部分に大人は関与する、という所に落ち着きました。
・共通した特徴として平等性があげられる
この場合の平等性の意味がよく解らなかったので、具体例を挙げて説明して欲しいと尋ねたら、社会性という範疇での平等性とのことで、なるほどと納得しました。
・誰に対しても差別することや偏見をもつことなく、公正、公平な態度で接し、正義の実現につとめること。
指導要領からの引用ですが、この中にある3つのフレーズの1つ目と2つ目を進化心理学でとらえるとどうなるか。システム2から取り組むとすると、この文のフレーズはこの順のままでいいかなど聞きました。良い感じでキャッチできました。
レポートのある部分に焦点が当たると、みんながそこに関連する話をはじめるのですが、その話が他のレポートの部分にも絡んでくることが多々ありました。昔のレポートは、それぞれが独立していて絡みようがないのが普通でした。絡むようになり、納得度が高まったのは進化心理学の学びの成果と思っています。
このような見え方は、若いころに学んだ弁証法と似ています。あのころは量質転化とか、技-内-技と言って、教育を考えていましたが、急速に見る目が成長したと思っていました。
ジョナサンの会は緩い会ですが、進化心理学という最先端の科学で教育論を語り合っている珍しい場となっています。
来月からは城ケ崎氏が参加します。総勢7名となります。